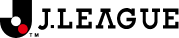3月27日(木)、エスパルス本社にて社員防災講習を実施し、社員が防災への知識を深めるとともに、今後取り組むべきことについて学びました。本講習は「防災の考え方について理解すること」「会社・個人それぞれでやるべきことを理解すること」の2点を目的とし、鈴与株式会社 危機管理室の織戸邦明室長に講師を務めていただき実施をしました。
日本の自然災害の現状
まず、日本における地震の状況として、全世界におけるマグニチュード6以上の地震のうち、日本での発生数が18.5%も占めていることや、今後30年以内に発生する確率が「80%程度」とされている南海トラフ巨大地震について多くの話題が取り上げられている点を説明いただきました。
また、実際に発生した阪神淡路大震災と能登半島地震の動画や南海トラフ巨大地震のシミュレーション動画を視聴し、「室内の物を固定すること」、「家屋の耐震補強をすること」、「静岡県の被害想定を把握して危機感を持つこと」が大切であるとお話いただきました。さらに、全ての災害を通して大切なこととして、「死者の声を聴くこと」を挙げていました。死者の声を聴くということは、「なぜ亡くなったのか」という観点から原因や対策を考えることであり、そのような考え方が必要不可欠であることを学びました。
防災の考え方は「敵・我・作戦環境」
海上自衛隊に所属した経歴をお持ちの織戸室長。「海上自衛隊では作戦を立てる際、『敵・我・作戦環境』を考えます。『敵』は敵の能力や脅威の見積もり、『我』は自分の部隊の強点・弱点、『作戦環境』は気象条件や海洋環境、電波環境のことです。それらのことを考慮して作戦を考えます。」と海上自衛隊における作戦への考え方を説明しました。また、このような考え方は防災にも当てはまり、下記のような観点を持つことが大切とお話されました。
「敵」
・ハザードマップを確認することが必須
ハザードマップでは少なくとも、震度・津波・液状化・土砂災害を確認
・紙のハザードマップは見づらいため、Webで確認する
「我」
・自分の会社、自宅の強点・弱点を考える
建物の耐震性能、室内の防災対策、近くの避難場所・避難所、備蓄品、初動対応といった観点について考える
・災害発生後の様々な判断の基準となるのは「建物が耐震性能の水準を満たしているか」
建物が生きていれば、備蓄品を置く意味があり、在宅避難も可能になる
「作戦環境」
・気温や風、雨量、地盤について考える
特に地盤については、液状化に大きく関わるため大切
「○○新田」「○○沼」「○○沢」という地名は水が多く地盤が緩い可能性が高い
「一個人として・地域社会の一員として・エスパルスの社員として」
最後に織戸所長は、「一個人として・地域社会の一員として・エスパルスの社員として」という観点から防災について考え、下記のような行動をしてほしいとお話をされました。
一個人として
・家族や友人との連絡手段の確立
・防災ポーチを作成し、持つこと
・自宅の防災対策をする
・緊急地震速報がなった時に「何をするのか」を考える
・「自分の命は自分で守る」という意識を持つ
地域社会の一員として
・「共助」を大切にする
自分の安全が確保できている状態であれば、地域社会の人を助ける
エスパルスの一員として
・安否確認システムへの登録と確実な応答
・各種訓練への積極的な参加
・会社の防災への取り組みの積極的な参加
織戸室長は「被災後に出来ることは限られています。しかし、被災前に出来ることはたくさんあります。是非、このことを認識いただいて、防災対策に取り組んでください。」と締めくくりました。
織戸室長、海上自衛隊での経験も交えた貴重なお話、ありがとうございました。
エスパルスは今後も社員が防災を自分事として考え、積極的に行動をするとともに、地域社会の防災についても情報の発信や行政・パートナーの皆様との取り組みを通して貢献していきます。