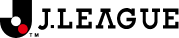エスパルスのホームタウン静岡市、ファミリータウン10市町/島田市、焼津市、富士市、富士宮市、清水町、長泉町、三島市、御殿場市、伊豆市、伊豆の国市には、富士山や駿河湾をはじめとした美しい自然、歴史や文化的な観光地、温暖な気候で豊かな食、そして都心へのアクセスも良好とたくさんの魅力があります。
ホームタウン、ファミリータウンをより知っていただくために、『夏休みにオススメの観光スポット』を各市町行政の皆様より情報をいただきましたのでぜひご覧ください!
Part1は【歴史・文化編】。近くにお住いの方も、まだ訪れたことのない素敵な場所があるかもしれません。全て訪れたら静岡の歴史・文化通になれそうです!夏休みの学習にも良さそうなスポットもたくさんありますので、ぜひご家族で訪れてみてください。
エスパルスのホームタウン・ファミリータウンで楽しい夏の思い出を!静岡でお待ちしています。
静岡市
静岡市東海道広重美術館
日本で初めて「広重」の名を冠した、浮世絵の美術館です。歌川広重の代表作「東海道五拾三次之内」(保永堂版東海道)、「東海道五十三次」(隷書東海道)、「東海道五十三次之内」(行書東海道)の他、晩年の傑作「名所江戸百景」など、風景版画の揃物の名品を中心に約1,400点を数えます。

清水港船宿記念館「末廣」
この施設は、明治19年(1886年)に清水次郎長が清水波止場に開業した船宿の復元施設です。次郎長がお茶の輸出による清水港の発展に尽力した晩年の姿と当時の資料を現在に伝え、清水港周辺の観光情報発信施設として活用されている建築物です。

島田市
蓬莱橋
島田と牧之原をつなぐ農道として明治12年に架けられた「蓬莱橋(ほうらいばし)」。全長897.4m、幅2.4mのこの橋は「世界一長い木造歩道橋」としてギネスに認定されています。「897(やくな).4(し)m」=「厄無し」、「長い木の橋」=「長生きの橋」と語呂合わせで縁起の良いスポットとしても人気があります。


大井川川越遺跡
江戸時代、大井川は橋を架けることも船で渡ることも禁止されていたため、旅人は「川越人足(かわごしにんそく)」と呼ばれる専門集団を雇って人力で川を渡っていました。「大井川川越遺跡(おおいがわかわごしいせき)」は川越人足の仕事場や当時の旅人が利用した施設を旧東海道沿いに復元・保存した野外ミュージアムであり、日本国内で唯一「川越し」の歴史を現代に伝える貴重な遺跡です。


焼津市
小泉八雲が愛したまち焼津
「耳なし芳一」や「雪女」などで知られる明治の文豪、小泉八雲は晩年の避暑地として、焼津をこよなく愛し、毎夏を過ごしました。市内には、八雲が訪れていた寺や神社、海岸のほか八雲に関する資料等を展示、紹介する焼津小泉八雲記念館など、ゆかりの地としてのスポットが多くあります。


花沢の里
山の谷地にある30戸ほどの山村集落です。万葉集にも詠まれた旧街道に沿って石垣が続き、長屋門風の建物などが立ち並ぶ昔懐かしい山村の風景が残ります。県内初の国の重要伝統的建造物群保存地区に指定されており、沿道の古民家カフェや古刹の法華寺なども見どころです。


富士市
富士川楽座
東名高速道路上り線からも一般道からもアクセスできる「富士川楽座」は、富士山を眺望できるレストランやカフェ、土産物売り場があります。また、ドライブイン機能だけでなく、体験館やプラネタリウムなどがあり、幅広い世代に支持されている複合型の道の駅です。


富士宮市
富士山本宮浅間大社
浅間大社は、全国に多数ある浅間神社の総本宮とされています。境内には、溶岩の間から湧出した地下水が池となった湧玉池(国特別天然記念物)があり、富士山の噴火を水で鎮めるという考え方から、池のほとりに置かれたと考えられています。近世は幕府の庇護を受け、徳川家康の寄進により慶長11年(1606)現在の社殿が造営されました。富士山山頂には八合目以上を境内地とする奥宮があります。

静岡県富士山世界遺産センター
静岡県富士山世界遺産センターは、2013(平成25)年6月にユネスコの世界遺産に登録された「富士山─信仰の対象と芸術の源泉」を後世に守り伝えていくための拠点施設です。センターでは、「永く守る」「楽しく伝える」「広く交わる」「深く究める」の4つの柱を事業として、国内外の多くの方に歴史、文化、自然など、富士山を多角的に紹介しています。

清水町
八幡神社・対面石
鎌倉幕府初代将軍「源頼朝」により創建されたと伝わる格式高い神社です。境内奥には、頼朝が弟義経と再会を果たした際に腰掛けたとされる「対面石」が鎮座しております。また、本殿では町指定文化財を始めとする貴重な品々を見学できるなど、町の貴重な歴史を現在に伝えています。

東海道の面影
町内には、江戸時代に整備された東海道の面影を見学できる場所があります。例えば、伏見の古刹、玉井寺と宝池寺には、街道の道標として造成された一里塚が2基残されています。また、長沢の黄瀬川橋のたもとには、街道整備の際に植えられた松林の一部が現在も自生しています。


長泉町
井上靖文学館
井上靖文学館は、1973(昭和48)年11月25日に開館しました。代表作『あすなろ物語』の中で、主人公が詠む「寒月ガ カカレバ キミヲシヌブカナ アシタカヤマ(愛鷹山)ノフモトニ住マウ」という歌にちなみ、長泉町東野の地に文学館が建てられました。開館から半世紀近く経った、2021(令和3)年4月、文学館は長泉町営となり新たなスタートを切り、企画展や講演会、ワークショップなどを開催しています。
.jpg)
原分古墳
直径約17mの円墳で、無袖型の横穴式石室が南に開口、長さ7.6m・最大幅1.7m・高さ2.0m、前庭部を含めた全長は約10.4mを測ります。石室内から人骨のほか家形石棺片、銀象嵌の柄頭や鍔、金銅装馬具、土師器、須恵器など多くの副葬品が出土しました。7世紀前半の築造ですが、道路建設に伴い南東へ約40mの場所へ移築・復元されました。

三島市
三嶋大社
伊豆一の宮として、源頼朝が挙兵に際し祈願をよせ、緒戦に勝利したことでも有名。桜の名所としても知られ、春には境内を彩る美しい桜が参拝者を魅了します。また、天然記念物の金木犀(樹齢1,200年)や、国の重要文化財に指定されている本殿など、見どころも豊富。歴史と文化を感じながら、静謐な空間で心安らぐひとときをお過ごしください。


三嶋暦師の館
平成18年に「国の登録有形文化財」に指定された建物です。館内には三嶋暦をはじめ、三四呂人形や三島茶碗などの展示もあります。三嶋暦は仮名文字で印刷された版暦としては、日本で一番古いものだと云われています。三嶋大社の近くに位置し、現代版三嶋暦の販売や無料の三嶋暦刷り体験も行っているのでお気軽にお立ちより下さい。


御殿場市
秩父宮記念公園
秩父宮記念公園は昭和16年から約10年間、秩父宮両殿下が実際にお住まいになられていた御別邸です。勢津子妃殿下がお亡くなりになられた後、御殿場市にご遺贈いただき、平成15年4月に公園として開園しました。敷地面積は約18,000坪(東京ドームの1.5倍)、豊かな自然と両陛下が愛された山野草をはじめ四季折々の花々を楽しむことができます。


東山旧岸邸
東山観音堂に隣接する旧岸邸は元首相、岸信介の自邸として1969年に建てられました。建築家・吉田五十八の晩年の作品で、伝統的な数寄屋建築の美と現代的な住まいとしての機能の両立を目指して設計された近代数寄屋建築の邸宅です。美しい庭園と合わせて見学できます。


伊豆市
修善寺温泉街
修善寺温泉は伊豆半島で最古の温泉地といわれており、弘法大師が病気の父を思う息子のために、桂川から霊泉を沸出させたことが起源とされています。そのときに大師が使ったのが独鈷杵(とっこしょ)と呼ばれる仏具で、「独鈷の湯」は修善寺温泉のシンボルとなっています。また、鎌倉時代に源頼朝の弟・源範頼と息子の頼家が幽閉された地でもあります。


伊豆近代文学博物館・井上靖旧邸(昭和の森会館)
伊豆近代文学博物館では、伊豆出身の作家や伊豆を愛した文豪の生原稿などの大変貴重な資料、文豪ゆかりの品々が数々展示され、文学が好きな人にはたまらない展示となっています。
昭和の森会館の敷地内には、美しく整えられた中庭、わさび田、水車、もみじ林があり、移築された井上靖旧邸を見ることができます。

伊豆の国市
韮山反射炉
韮山反射炉は、平成17年7月に、世界遺産文化遺産に登録されました。江戸時代末期に築造が開始され、実際に稼働した反射炉としては国内で唯一現存する貴重な近代化産業遺産です。

江川邸
江戸から明治に至るまで、世襲代官として韮山の地を治めた江川家代々の屋敷“江川邸”は“江川家住宅”として国の重要文化財に指定されています。また江戸幕府の代官所だったことから、韮山役所跡として国の史跡に指定されています。

情報を提供いただいた各市町の皆様へ御礼申し上げます。これからも地域とともに。