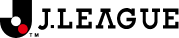プロサッカー選手になるまでの道のりは人それぞれ。だからこそ各々がルーツに基づいた“サッカー観”を持っている。選手たちの過去を紐解き、現在のプレーヤー像が形づくられた背景に迫るコンテンツ『ヒストリア』。第2回は梅田透吾選手編。
8月9日公開/取材・文=平柳麻衣

小学3年生でサッカーをやめようとしたけど……
5歳の時にサッカーを始めました。“始めた”より“始めさせられた”と言ったほうがしっくりくるかな。というのも、幼馴染のお父さんがクラブチームのコーチだったからという理由で連れて行かれたので、僕自身は全然乗り気じゃなかったんです。小さい頃によくある、ごちゃごちゃしたお団子サッカーが苦手で、いつも1番後ろに立ってボールが来るのを待っているタイプでした。それに、実はサッカーよりも野球をやりたかったんです。卓球やバドミントンにも興味があって、もしかしたらこの頃からボールを手で扱うことに惹かれていたのかもしれないですね。
小学3年の時、親に「もうサッカーをやめたい」と言いました。この頃が僕にとっての大きな転機です。一つは、野球チームの練習会に1、2回参加したけど、結局なあなあになって入らなかったこと。そして小学4年生から公式戦や地区トレセンが始まるので、それに向けて“ポジション”というものが登場したこと。キャッチボールが得意だったというのもあるけど、GKというのはみんなあまりやりたがらないポジションで、そういうところを拾っていく僕の性格もあって、気づいたらグローブをはめていました。

その頃、運動能力はあるほうだと信じていたけど、クラスの中で足が速いほうに入るかどうかギリギリのところにいて、体力もなかった。だけど、器用だったからGKは感覚でできてしまうところがあって、小学4年生の時に一つ上の学年の地区トレセンに入り、5年生になったら県トレセンに入り、もうサッカーから逃げられないなと。自分としても心のどこかで何となく「やめないほうがいいんだろうな」と感じていたところはあります。
小学生の頃は自主練なんて1回もやったことがなかったし、早く家に帰ってポケモンで遊びたいと思っていたぐらい。でも、「サッカーを楽しみたい」という気持ちだけはあって、やっぱり勝たないと楽しくないんですよね。そう考えると、当時から負けず嫌いなところはあったのかなと思います。

「同じ土俵で戦わないこと」を学んだ下積み時代
小5、小6はありがたいことに県選抜に入ることができたんですけど、逆にそこから先の東海地区などには一度も選ばれていません。「上には上がいるんだな」と思い知らされたのは、ある意味、挫折と言えるかもしれないですね。
中学校に進学する時、部活動ではなくクラブチームでサッカーをやりたいと思っていて、最初は地元から近いジュビロ沼津(現アスルクラロ沼津)に入ろうとしていました。でも、周りから「エスパルスのセレクションを受ければいいじゃん」と言われ、「落ちる」とか「失敗する」ことがちょっと恥ずかしい年頃だったから、自分から受けるつもりはなかったんですけど、周りに言われたことで「受けてみてもいいかな」って。でも、その覚悟ができたのはセレクションの締め切りを過ぎた後。結局、親に電話してもらって受けさせてもらえることになったので良かったですが、受かった時には自分が一番ビックリしました。

僕と同学年でジュニアユースに入ったGK天野友心はすでに身体ががっしりと出来上がっていたけど、僕は小6のセレクションの時点で150cmないぐらい小柄でした。周りと体格差がありすぎて、もはやライバルとも思わない。そんな時、カケさん(掛川誠GKコーチ)と出会えたことが僕にとっては大きかった。「身長はいずれ伸びるから大丈夫。お前は今じゃないよ」と言われ、基礎技術を徹底的に教え込まれたおかげで、僕自身も「中3までには自分の立ち位置が変わっているだろう」と先を見据えてモチベーションを維持することができていました。
ジュニアユースに入った頃の僕は、それはもうひどかったですよ。小学生の頃はゴールが小さかったからそんなに困ることはなかったけど、中学からゴールが7.32mになって、ボールも5号球になる。すると、クロスがそのまま入ってしまったりして、キャッチすることすらできない。5号球が飛んできたら勢いに勝てないし、シュートに手が届かない。
「もう本当に無理だ」と思ったんですけど、カケさんは一度も「筋力をつけろ」とは言わず、タイミングや技術をずっと指導していただきました。その頃から僕が意識するようになったのは、「同じ土俵で戦わないこと」。例えば正面キャッチする時には、「正三角形を作って」ってよく言われますけど、それだけではパワーがないから取り切れない。じゃあ、三角形を作る時に同時に身体も動かして、ガっと力を入れることでボールの威力を吸収してみよう、とか。手は三角形のままだから言われたことは守りつつ、自分の中で噛み砕いて、結果的に取れればいいでしょっていうスタンスでしたね。

カケさんは過程を説明するのがすごく上手いので、「何でこうやって動けるか分かる?」と聞かれて「分かりません」と答えると、「ここに重心がかかっていて、ボールがここにあるから…」といった説明を全部分かりやすくしてくれました。中1、中2の下積み時代があったからこそ、小学生の頃は何となくでやっていた動きをしっかり頭の中で整理してできるようになり、中3の頃にはやっと身体の成長も追いついてきて、天野友心と五分五分で試合に出られるようになりました。
ちなみに中2の時にグリコチャレンジツアーで初めて海外(ブラジル)へ行きました。海外の環境や考え方の違いに驚いたし、同年代の選手でも身体つきが全然違いました。同期の中で大きいほうだと思っていた監物拓歩が、ブラジル人と比べたら小さく見えるぐらいだったのはビックリしましたね。

自分のやり方で周りを認めさせる
僕の代は、エスパルスアカデミー史上初めて同学年でジュニアユースからユースに2人のGKが上がりました。中3の時こそ出場機会は五分五分だったけど、やっぱり僕は基本的に過小評価だから、「上には上がいる」というメンタルは変わらないまま。でも、「高いレベルでやりたい」という気持ちはあったから、やっぱり根本的には負けず嫌いなのかもしれません。
高1の時のGKコーチは羽田(敬介)さんで、まずはユースのプレースピードやパワーなどの基準を教えてもらいました。もちろんジュニアユースに比べたらレベルは高いんですけど、それに対してあまり驚きはなかったんですよ。ジュニアユースの頃から「シュートが速いならこうやって動けばいい」という、その時々の対応法がきちんと頭で整理できていたから、ユースのレベルにもすんなり順応できたのかなと思います。

高2からはGKコーチがカケさんに代わって、今度はジュニアユースの頃と少し指導内容が変わり、「アスリートとしての身体は持っていたほうがいい」ということで、身体操作性を意識したトレーニングも取り入れられるようになりました。そして高2からプレミアリーグEASTで出場機会を得るようになり、FIFA U-17ワールドカップのメンバーに選ばれました。それまでの予選では一切呼ばれたことがなかったのに、いきなりの本大会選出。嬉しい反面、「何で?」という気持ちも大きかったですね。
代表メンバーは谷晃生や鈴木彩艶、久保建英、中村敬斗、菅原由勢、小林友希、平川怜、鈴木冬一、福岡慎平といった錚々たる面々。エスパルスからは監物も一緒に選ばれました。僕は初招集だったからこそ、一歩引いて「代表に入る人ってこういう考え方を持っているんだ」と見るようにしつつも、やっぱり“自分の土俵で戦おう”ということは意識しました。

良いか悪いか分からないですけど、僕は「この人に認められるために」とか「このチームで評価されるために」やろうとするのが上手くないんです。常に自分に矢印を向けて、自分を高めることが最優先で、その結果として評価してもらえたら嬉しいなって。「それだと頑張りが見えない」とか「評価できない」と言われることもあったけど、自分のやり方で周りを認めさせてやるんだという気持ちは強かったし、そうやってプロまで上がってきたと自負もあります。
身体が小さくて、足も周りと比べて速くなくなって、周りから見る目が変わりそうなタイミングでGKというポジションに出会い、頭を使ったプレースタイルにシフトしたこと。GKとは運命的な出会いだったなと思います。

GK以外のポジションをやっている姿は想像がつかない
ユースからトップチームへの昇格が決まったのは、どちらかというと遅いほうだったと思います。おそらく高3の4月、5月ぐらいの頃には昇格の話はなかったはず。だけど、ジェリー ペイトンさんがトップチームのGKコーチに来て、僕のことを評価してくれました。それこそ身体の弱さやパワーがない部分を帳消しにするぐらい、技術や身体の使い方、GKとしての感覚の部分を見て、「結局、止めればいいんだよ」と。その感覚は、ちょっと日本人指導者と違うというか、外国人ならではの感性なのかなと思いました。
そしてプロになってからサッカー観の面で一番影響を受けたのは、ピーター クラモフスキー監督。自分のサッカー観をちゃんとチーム全体に共有しようとしてくれたから、すごく分かりやすかったです。ただ、サッカー観というのはチームとしての決まり事や試合の流れ、選手たちの雰囲気によって変わるものなので、あまりイメージを持ちすぎないようにはしています。

僕は高2の終わり頃、代表など慣れない環境で蓄積されたストレスからか、体調不良でサッカーができない時期がありました。それ以降、頑張りすぎる手前でやめるということを覚えて、自分の身体に気を使いながら、ビビって過ごしてきたところがあったけど、プロ4年目に右膝前十字靭帯断裂のケガを負って、よくも悪くも一旦リセットされたというか、去年ぐらいからやっと完全に吹っ切れて、今は気持ち的にも身体的にもマックスでトレーニングができています。
もちろん元々の性格で効率性を求めてしまうところもあるけど、結局は他人に評価される世界で生きているから、やっと折り合いがつけられるようになってきた感覚です。試合中に感情を動作で表す場面が増えたのもその一つかもしれません。

ただ、常に“最悪”を想定しながら自分に矢印を向け続ける姿勢は変わっていないです。例えば横浜FC戦(7月20日)での前半のセーブに関しても、自分が触ったからゴールから逸れたことよりも、「今のゾーンの作り方ちょっとミスだったかな」と考えてしまうから、喜んでる暇がないんです。すごく良いセーブをしたとしても、「俺、少しポジションずれてたかな」って考えるから、味方を鼓舞する余裕もない。
変な言い訳をせず、他人のせいにせず、常に自分のことを考えてプレーするのは、GKとしての基礎基本を学んだ中学生の頃からずっと変わらないこと。そんな自分だから、GK以外のポジションをやっている姿は想像がつかないし、やっぱりサッカーが好きなんだなと思いますね。

エスパルスアプリでは試合日の舞台裏に迫った人気コンテンツ『THE REAL』のほか、試合前後の監督・選手コメント、選手インタビュー『三保クラブハウス通信』、イベント裏側動画など様々なオリジナルコンテンツを日々配信中です。
ぜひ、ダウンロードしてお楽しみください!