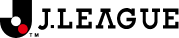プロサッカー選手になるまでの道のりは人それぞれ。だからこそ各々がルーツに基づいた“サッカー観”を持っている。選手たちの過去を紐解き、現在のプレーヤー像が形づくられた背景に迫るコンテンツ『ヒストリア』。第4回は宇野禅斗選手編。
11月27日公開/取材・文=平柳麻衣

ブラジルのストリートサッカーが原点
僕のサッカーの原点は、もちろん二人の兄がサッカーをやっているところを見て育ったのが始まりですが、サッカー観という意味で言うと、小学校低学年ぐらいの時にずっとDVDで観ていたブラジルのストリートサッカーが原点だと思います。両親がサッカーを観るのが好きで、Jリーグよりも録画された昔のワールドカップの映像をよく観ていたので、僕もネイマールやロナウジーニョが好きだったし、小学校高学年の頃には「留学してブラジルでサッカーがしたい」と思っていました。小学生の頃は8人制のサッカーで相手を5人ぐらい抜いてゴールを決めるような点取り屋でしたし、その後いろいろなことを経てプレースタイルは変わっていきましたが、相手を騙したり、いなしたりしながら“サッカーを楽しむ”スタンスは今も自分の中にあります。

お兄ちゃんがいたおかげで、年上の人とサッカーをする環境がずっと身近にあったのは僕にとって大きかったです。チーム練習以外の日は、小学校の校庭で暗くなるまで一対一をやったり、数字が書かれた壁に向かってどっちが先にボールを当てられるか競ったり、公園の木を避けながらぐるぐるドリブルをし続けたり。また、クラブチームの練習がある日は、終わった後の帰り道、途中にあるコンビニまで3キロぐらいの道のりを毎回競走していました。
あとはトレセンも含め、県外のチームと対戦する機会があったことも大きなターニングポイントになりました。福島ユナイテッドFCの育成組織に所属していた小学5年生の時、初めて福島県で優勝して全国大会に出場することができました。でも、全国大会に行ったらボッコボコにされて。トレセンもそうですけど、同じ年代で同じサッカーをやっている人間なはずなのに、他県の選手たちはみんな上手くて、速くて、圧倒されるばかりだったから、自分はまだまだなんだと実感したし、中学から県外に出たいと考えるきっかけになりました。

転機となったボランチへのコンバート
青森山田中への進学は、もう即決でした。サッカーのスタイルは関係なく、練習参加に行った時に「ここでやりたい」という気持ちになったんだと思います。青森山田の選手が厳しい声掛けをしながら練習をやっていた記憶があったんですけど、「帰ってきたらニッコニコしてたよ」と母親に言われます。
次のターニングポイントは中2の冬ですね。中2の時はいわゆる病み期というか、沼にハマっているような時期だったと思います。精いっぱい頑張って上のカテゴリーの練習に入れてもらっても、周りと圧倒的に差があると感じてしまって上手く自分らしさを出せない。かと言って、下のカテゴリーでは物足りないと感じていて、どちらでも上手くいっていなかったんです。当時はセンターバックをやっていて、「このままセンターバックをやり続けて、プロになれるのか?」とすごく悩んで。そんな時、コーチから「ボランチやってみるか?」と言われてアンカーに入ったのが転機になりました。

ボランチへのコンバートはポジティブなことしかなかったと思います。このままの身長でセンターバックは無理だろうと感じていたところもあったし、やっぱりどうしても自分の中に攻撃的なプレーもしたいという思いがあるから、センターバックだとそれが生かされていないと感じる部分もありました。もちろんセンターバックからボランチへの移行はそんなに簡単ではなくて、中3の1年間も、高校に上がってからも、とにかく「首を振れ」「周りを見ろ」と口酸っぱく言われていました。
一方で、センターバックでの経験が生きた面もあります。センターバックの時は相方がカバーしてくれる分、僕はガンガン潰しに行く役割を担っていたので、どれぐらい寄せたら相手は嫌がるのかとか、どのぐらいの距離ならボールを奪いやすいのかとかを考えるのが楽しくて。それが今も“刈り取る”という自分の守備の礎になっていると言えるかもしれないです。また、同い年に僕とはタイプの違うボランチの選手がいて、僕が勝手に切磋琢磨してたんですが、「そいつより上手くならなきゃいけないし、“奪う”ことに関しては圧倒的でなければいけない」と思えていたおかげで、常に「自分の武器を突出させないと」という危機感を持ち続けることができました。

刈り取ることを武器にしながらも、自分一人で奪い切ることに固執しているわけではないんですよ。それを学んだのは、高校3年で初めて年代別代表に呼んでもらった時です。試合の中で僕が食いついたスペースを使われてしまったシーンがあり、代表スタッフの方に「自分のスペースを空けるということをもっと理解しなきゃダメだ」と教えてもらいました。それまでは、どの局面でも自分の運動量で2対1の局面を作れるのが強みだと思っていたけれど、時には味方に任せることも大事なんだと学びました。
また、代表ではセンターバックやサイドバックからボランチにどんどんパスが入ってくるけど、前を向ける状況なのに前を向くことができないということもありました。それだけ周りが見えていない、立ち位置が悪い、情報量が少ない、パスを受ける準備すらできていないんだなと痛感しました。新しい環境に行って自分の通用しないことばかりにぶつかると、もちろん落ち込むことはあります。だけど、それよりも「できるようになりたい」というか、「自分だってできる」という気持ちのほうが強いから、“できない自分”が見つかるたびに楽しんで乗り越えてきた気がします。

毎日3時間、雪の上を走るだけ
青森山田は筋トレをガッチリやって、身体がゴツくて、サッカーとして面白くないと思われることが多いんじゃないかと思います。でも、僕が中1の時に全国高校サッカー選手権で初優勝して、廣末陸さんや髙橋壱晟さんがいる代だったんですけど、本当に強くて、圧倒的で、すごくカッコ良かったんですよ。中学でも求められるのは高校と同じで、上手い云々の前に“戦える”選手であること。プレーもそうだし、声を出すのも当たり前。言われっぱなしの選手なんて生きていけないですから。
技術面に関しては、とにかく練習量が多いのと、練習中にもミスが許されない空気感があることで磨かれていったと思います。基本的なパス練習でもパスのスピードがすごく速くて、それをトラップできる技術をつけるというのは大前提。止める・蹴るの部分でミスをしたら「そんなんでミスするな」と先輩たちからすごく言われますし、毎日毎日プレッシャーを感じる中で練習していくうちに、自然とそのスピードでできるようになっていったと思います。自分もまた学年が上がれば後輩たちに厳しく言うようにしましたし、「青森山田のトップチームはこういう場所なんだ」というプライドを全員が持ってやっていました。

ポゼッション練習やクロス練習、ゲーム形式もやったりしましたが、とくに重点を置いていたのは守備の部分だったと思います。いかにボールを奪うか。簡単にシュートを打たせない、クロスを上げさせないことや、寄せる基準は青森山田に行ったおかげで身体に染み付きました。ゲーム形式の練習で相手チームにパスを回されることが続くと、「何をやっているんだ」と指摘されるんですけど、逆にボールを奪えることが続くと、今度は逆側のチームが「攻撃の質が低い」と言われるので、攻守どちらも高く要求されていました。
あとは青森山田と言えば、雪中の走りですね。12月の始まりから2月の終わりぐらいまでは雪が積もるので、選手権が終わって新チームが始動しても、最初の1カ月ぐらいは毎日3時間、雪の上を走るだけ。ボールを触ることすらできないというのは本当にキツいですけど、そのおかげで反骨心みたいなものが生まれます。「他のチームがボールを使って練習できている間、俺らはこんなに苦しい走りをやってきたんだ」って。

春先の遠征ではもちろん勝てないし、チームとしてなかなか上手くいかないんですけど、コーチ陣からは「お前らはボールに触ってこなかったんだから、走るしかないんだよ」と言われるから、ガンガン戦いに行く。そこでもし「雪のない暖かい地域のチームに行けば良かったな」なんて考えているような選手がいたら、スタッフに何か言われる以前に、選手同士の中で弾かれます。「戦えないなら抜けろよ」と。この前、実家に帰った時に高1の時の試合のDVDを親に観せてもらったんですけど、先輩に対してもものすごい顔で声を出している自分の姿にびっくりしました。
高校に入って最初はBチームからスタートしましたが、5月にはトップチームに呼ばれました。どう評価してもらえたのか自分ではあまり分からないですけど、サッカーに対しては誰よりも真摯に向き合ってきた自信があるし、例えばチームの朝練が6時からだったら、5時に一人でグラウンドに来てシュートやパス、ドリブルの練習をずっとやっていました。だから、「周りが遊んでいる時間も、俺はサッカーをやっている」ということが僕の自信の一番の源になっていたと思います。

戦術や型にハマってばかりのサッカーでは面白くない
以前の僕は、どんな形でも点が入ればいいだろうと思っていました。綺麗に崩して点を取るのも、GKからのロングボールに裏抜けして取るのも、PKも、1点は1点でしょって。でもエスパルスに来て、秋葉忠宏監督と出会って、もっとサッカーを勉強したいと思うようになりました。秋葉監督は毎試合毎試合、もちろん大前提としてエスパルスが目指すサッカーは掲げながらも、相手によってより細かくこういう形で守りましょう、点を取りましょうと示してくれるので、それがバチッとハマる瞬間って面白いなと。身体を投げ出して戦うというベースがあって、そこに相手の弱点をこうやって突きましょうというロジックがあって、それを理解する力や体現する能力、情報量、知識を持った人間が、最後の最後に言うのが「点なんて入れば何でもいい」だと思うんです。それは(松崎)快くんや(矢島)慎也くんの考え方に触れられたのも大きいと思います。だから僕はもっとその土台の部分を色濃く積み重ねたいと思いながら今、サッカーと向き合っているところです。
僕は犠牲心みたいなものが好きな人間なので、例えばアシストではなかったとしても、自分の展開から点につながったみたいな時が一番喜べるというか、“おいしいな”と思えていました。別に誰かに評価されたくてサッカーをしているわけではないから、そのプレーの良さに気づいている人がいなければいないほど良い。だけどプロになって、それだけでは上に行けないし、日本代表にはなれないと思ったので、思考を変えました。

町田にいた一昨年、僕が点を取って勝った試合でJ1昇格が決まったんです。その時、点を取る快感ってサッカーをやっている中でダントツで、何ものにも代えがたいなと思ったし、それ以前の僕は本気で点を取りたいと思えていなかったんだなと気づくことができました。
だから昨夏エスパルスに加入した時も、周りに認めてもらうために1試合目で絶対に点を取ると決めていたし、それを実現できたおかげでスムーズにチームに馴染むことができました。あの時の点を取る感覚を常に持ちながらプレーしたいと今季も取り組んできたんですけど、J1はそう甘くはないとも感じています。
僕が幼少期に憧れたネイマールもロナウジーニョも、今観ると、1試合の中で無駄なプレーをしているシーンも多いなと感じます。もっと簡単にパスを出せば、チームとしてチャンスになるシーンがたくさんあるのにって。だけど、戦術をはじめサッカーの勉強をすればするほど、戦術や型にハマってばかりのサッカーでは面白くない。そこにネイマールやロナウジーニョみたいな、一見無駄に見えるプレーをする選手がいるからこそサッカーって観ていて楽しいスポーツなんだなと思います。僕が最初に好きになったのはそういうサッカーだから、選手として、その部分はなくさずに成長していきたいです。

*********************
宇野自身も今夏のEAFF E-1サッカー選手権でA代表に初選出され、デビューを果たしたが、以降はケガの影響もあり、選考から漏れている。同年代や年下の選手が名を連ねるメンバー表を見て、こう呟いた。
「悔しさが100。こういう時、毎回僕は“こっち側”なんですよ。『何してんだよ俺』って毎回思う。でも、一緒にやってきた仲間が選ばれているのは、嬉しさもあります。素直に『みんな努力してるんだな。すごいな』って思えるし、自分にもチャンスがあるってことだから。僕も最終的には絶対、あっち側に行きます」
「マジで頑張ろう」。まだ見ぬ景色を見るために、宇野は自分自身を奮い立たせている。
エスパルスアプリでは試合日の舞台裏に迫った人気コンテンツ『THE REAL』のほか、試合前後の監督・選手コメント、選手インタビュー『三保クラブハウス通信』、イベント裏側動画など様々なオリジナルコンテンツを日々配信中です。
ぜひ、ダウンロードしてお楽しみください!